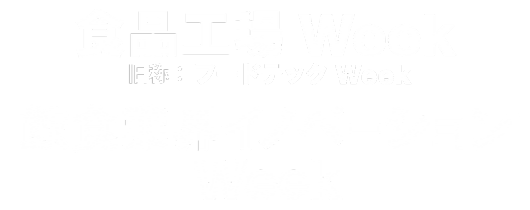スーパーが人手不足に陥る原因は?解消方法やおすすめ業務効率化ツールを紹介
スーパーは人手不足が慢性化している業種のひとつです。人手不足が解消されなければ継続的な店舗運営が難しいと困っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、スーパーが抱える人手不足の原因や人手不足の解消方法を紹介します。人手不足解消の方法として導入が進んでいる業務効率化・自動化のシステムやツールも紹介するので、人手不足に悩んでいるスーパーや飲食店経営者の方はぜひ参考にしてください。
スーパーの人手不足問題の現状
スーパーは入職者数も多いですが、離職率も高い業界です。厚生労働省が公表している資料によると、卸売業・小売業の令和5年1年間の入職者数・離職者数と割合は以下のとおりです※1。
また、正社員も不足していますが、特にパート・アルバイトが不足しています。卸売業・小売業の労働者過不足状況は以下のとおりです※2。
一般社団法人全国スーパーマーケット協会の資料では、店舗勤務のパート・アルバイト比率が業界平均で70%を上回っていることもわかっています※3。
特に、都市圏に比べて地方圏のスーパーは必要人員を採用できた割合が少なく、2023年には、98.1%の企業が「人手不足対策の取り組みとして採用活動を実施している」と回答しています※3。
近年の状況からみても、スーパーマーケット業界は慢性的な人手不足に陥っていることがわかります。
スーパーが人手不足に陥っている主な原因や理由
業界問わず、離職の原因に多いのは自己都合をはじめとする個人的な理由での離職です。なかでもスーパーが人手不足に陥る主な原因や理由には、以下のものが挙げられます。
- 業界全体で給与・時給の水準が低い
- 長期間の労働を前提としていない
- 土日祝日の出勤が求められる
- キャリアパスの不明確さ
- 体力面での負担が大きい
- 様々な人が密接な環境で働き不和がおこりやすい
- カスタマーハラスメントやクレーム対応がつらい
なお、食品業界全体や飲食店での人手不足については以下の記事で紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。
▶関連記事:食品業界が抱える人手不足の原因とは?日本の現状と企業が取り組める対策を解説
業界全体で給与・時給の水準が低い
離職率が高い原因のひとつに、給与・時給の低さが挙げられます。スーパーマーケット業界の初任給は大卒が約20.4万円、高卒が約17.8万円です※1。全体の平均は大卒で約21.25万円、高卒で約18.33万円のため※2、全体平均より低いことがわかります。
また、スーパーのパート・アルバイト募集時の平均時給は以下のとおりです※1。
全体平均は1,412円なので※3、パート・アルバイトの賃金も全体平均と比べて高くありません。さらに、業種別にみたパート・アルバイトの平均時給では、「教育、学習支援業」が2,584円、「医療、福祉」が2,017円と高いのに対し、小売業は1,204円とその他の業種に比べても比較的低い傾向にあります※3。
パート・アルバイトを中心に運営されている反面、給与の低いことは離職率の高さや働き手が集まらない原因になっている可能性が高いでしょう。
長期間の労働を前提としていない
スーパーで働く人は長期間働くことを前提としていないことが多い傾向にあります。特にパートやアルバイトは扶養者がいることも多く、扶養から外れないために短期間労働が前提の人や職場に不満があると辞めてしまう人も少なくありません。
例えば、厚生労働省の調査によると19歳以下のアルバイトでは「仕事内容に不満がある」や「給与以外の労働条件に不満がある」などの理由で辞めている人の割合が、他の年齢層より多い傾向にあります。
いつでも辞められる状況にある層が多い点は、スーパーの離職率の高さにつながっているかもしれません。
土日祝日の出勤が求められる
土日祝日が休みづらいことが、離職率の高さや人が集まらない原因になっている可能性もあります。スーパーはサービス業のため、土日祝日は出勤になりやすい職場です。
1日あたりの客数も平日よりも土日の方が多いため、人手が足りないスーパーでは土日祝日が休めないために辞めてしまう人もいるかもしれません。年間休日日数も平均と比べて少ない他、祝日やゴールデンウィークも休みにくい業種です。
政府の統計では、以下のデータが公表されています※。
休日の少なさは、人手不足の要因のひとつになっていると考えられるでしょう。
キャリアパスの不明確さ
スーパーマーケットでの仕事は、昇進やスキルアップの機会が少なく感じられることが多いため、キャリアアップを目的とした勤続年数が短く、新しい転職先にも選ばれにくい傾向があります。
レジ係や陳列、店舗管理など、どのポジションでも日常業務が比較的固定化されているため、転職による新しいスキルの習得や専門性の向上が期待しにくいためです。
一部の大手スーパーやチェーンでは、マネジメント層やバイヤー、商品開発などの高次の役職に昇進できる道もありますが、中小規模のスーパーマーケットの職場内キャリアには限界があります。
体力面での負担が大きい
スーパーでは、レジでの立ちっぱなしや品出しなど体力を要する業務が多くあります。特に24時間営業の店舗では、深夜や早朝シフトが生活リズムの乱れにつながるため、避ける人もいるでしょう。
また、人手不足が慢性化している店舗では、一部の従業員に業務負担が集中し、体力的な負担がさらに大きくなることも少なくありません。
体力面の負担や人手不足による従業員の負担増加が、負のスパイラルを起こしている可能性があります。
様々な人が密接な環境で働き不和がおこりやすい
スーパーの全従業員に占める60歳以上の割合は約27.3%です※。パート・アルバイトの募集では70歳を上限にしている店舗も少なくありません。一方、働くために特別な訓練や実務経験を必要としない業種なので、学生アルバイトや高卒の新卒者も多い業種です。
人手不足対策として高齢者の採用、定年年齢・雇用上限年齢の引き上げ・撤廃、外国人労働者の採用などを取り入れている店舗もあります。
スーパーはひとつの限られた空間で働くので、従業員同士の関係も近くなりやすいでしょう。幅広い年齢層・価値観の人が一緒に働けば、人間関係のほつれが生じる可能性も高くなります。人間関係のほつれが離職につながり、人手不足に陥るケースも少なくありません。
カスタマーハラスメントやクレーム対応がつらい
スーパーに、子どもからシニアまで様々な人が訪れる職場です。なかには気難しく、品切れ商品や従業員の対応に厳しくあたってくる人もいます。
顧客等からの著しい迷惑行為は「カスタマーハラスメント」と呼ばれ、従業員の健康不良、休職、退職の原因につながるとして問題視されています。厚生労働省から、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルの作成も推奨されているほど深刻化している問題です。
肉体面だけではなく、精神的な負担が離職につながり、人手不足の原因になっている可能性もあるでしょう。
スーパーが人手不足を解消するためにできる対策
スーパーの人手不足への対応策として、主に採用活動の拡大が取り入れられています。2023年の取り組み内容と、各取り組みを実施していると回答した企業の割合は以下のとおりです※。
採用活動を含めたスーパーの人手不足を解消する対策は以下のとおりです。
- 労働環境の改善
- 採用活動の強化
- 高齢者・外国人労働者の採用
- 人事評価の透明性
- 業務の効率化・自動化
いずれかひとつではなく、複合して進めていくことが大切です。
労働環境の改善
労働環境の改善は離職の減少につながります。具体的な改善方法は以下のとおり様々です。
- シフトの柔軟性を高めること
- 無駄な作業の削減・効率化
- 有給休暇を取りやすい環境作り
- 業務内容のマニュアル化
店舗によって効果的な改善案は異なります。人手不足の要因を洗い出すためには、現状の問題点の確認し、従業員にアンケートなどを実施して改善点を認識することが大切です。改善が必要なポイントを見つけて、自店舗にあわせた改善策に取り組みましょう。
採用活動の強化
採用活動の強化は多くの企業で取り入れられている人手不足の対策です。具体的には、求人媒体への掲載強化が挙げられます。紙媒体の求人雑誌への掲載だけではなく、インターネット上で閲覧・応募可能な求人サイトへも掲載を検討しましょう。
スマホの普及により、インターネット上で求人情報を集める人も増えています。求人雑誌への掲載や近隣へのポスティングなどアナログな媒体での募集に加え、インターネット上の求人サイトへ掲載することでターゲット層を広げられます。
高齢者・外国人労働者の採用
思うように人材が集まらない場合、高齢者や外国人労働者の採用も検討しましょう。定年退職後に働ける場所を探している高齢者もいます。近年留学生や就労ビザを持った外国人を採用している企業も少なくありません。
2024年7月23日には、総合スーパーマーケットおよび食料品スーパーマーケットで飲食料品製造業分野の特定技能外国人の受け入れも可能になりました。ただし、販売業務に従事させることはできない点に注意しましょう。
人事評価の透明性
透明性の高い評価制度を確立することで、社員やパート、アルバイトのモチベーションやエンゲージメントが向上し、離職を防止する可能性があります。
人事評価の透明性とは、評価基準や評価方法、評価結果などが対象者へ明確に伝えられていることです。評価基準やプロセスを従業員へ共有した透明性のある評価制度には、次のようなメリットがあります。
- 社員の能力や成果、評価の根拠を可視化できる人事評価システムの構築
- 給与に評価を反映させる仕組みの導入
他にも、離職を防止するには、会社のビジョンやパーパスの周知、柔軟な働き方の提供やコミュニケーションの活性化など、さまざまな取り組みが有効です。
業務の効率化・自動化
業務を効率化・自動化するツールやシステムを導入するのも人こと不足対策のひとつです。システムやツールの導入は、人的ミスが減少し、従業員の負担が軽減されるだけでなく、サービスの質も向上します。
導入には初期費用が必要ですが、長期的には人件費の削減や人手不足の解消に大きく貢献するでしょう。思うように人が集まらないのであれば、業務を効率化・自動化するツールやシステムの導入を検討してみてください。
スーパーの人手不足を解消するツール・システムの一例
スーパーの人手不足を解消するツール・システムの一例には、以下のものが挙げられます。
- キャッシュレス決済
- セルフレジ・セミセルフレジ
- スマートショッピングカート
- 在庫管理システム
- シフト管理システム
- ダイナミックプライシング
以降でそれぞれの内容をわかりやすく紹介します。
キャッシュレス決済
キャッシュレス決済の種類は以下のとおりです。
- クレジットカード
- 電子マネー
- QRコード決済
キャッシュレス決済の比率は年々増加しており、経済産業省の調査によると、2010年に約1割程度だったキャッシュレス決済比率は、2023年度には約4割まで伸びています※。
スーパーでもキャッシュレス決済比率は年々増加しています※。
決済手段の種類ごとの導入割合と利用金額に占める割合は以下のとおりです※。
現金払いは依然として多いものの、年々キャッシュレス決済の割合は増加しています。キャッシュレス決済導入により期待できるメリットは以下のとおり、人手不足解消だけではありません。
- レジの待ち時間削減による顧客満足度の向上
- レジの回転率アップによる売上の向上
- 機会損失の回避
- 会計ミスの削減
従業員だけではなく、顧客にとってもメリットが多いため、まだ導入していない場合は検討してみてください。
セルフレジ・セミセルフレジ
セルフレジとは、バーコードの読み取りから会計までを顧客自身が行うシステムです。一方、セミセルフレジは、バーコードの読み取りを従業員が行い、お会計を専用の機械で行うシステムをさします。
いずれも導入によりレジ作業の効率化や従業員の負担軽減が期待できるシステムです。セルフレジ・セミセルフレジを導入すれば、ピーク時でも人員を増やす必要が少なくなります。また、人件費やシフト管理も不要になるため、長期的に運用すれば人手不足の解消や人件費削減につながるでしょう。
一般社団法人全国スーパーマーケット協会の調査によると、セルフレジの設置状況は2023年で31.1%と3割程度です※。データを見ると年々増加していることが伺えます。
スマートショッピングカート
スマートショッピングカート(スマートカート)とは、商品のスキャン機能や会計処理機能が備わったタブレット端末を搭載したカートです。顧客はお買い物をしながら商品をスキャンでき、合計金額を確認できます。
出口付近のレジではすぐにお会計ができるので、セルフレジよりも待ち時間が少ない点が特徴です。なかには専用のプリペイドカードでお会計できる機能が付帯したカートもあります。
ただし、導入コストが比較的高い傾向にあるため、規模の小さい店舗では導入しづらい点がデメリットです。規模が大きく、導入により人手不足やレジの待ち時間解消による顧客満足度の向上が期待できる店舗であれば導入を検討してみても良いかもしれません。
在庫管理システム
在庫管理システムとは、商品の在庫管理をスマホやパソコンで行えるシステムです。POS(販売時点情報管理)と連携すると、いつ入荷し、いつどのくらい売れたのかの在庫管理や棚卸し業務の効率化が可能になります。
データの分析によって販売予測や適正在庫、ロスの改善にも役立つので、人手不足の解消だけではなく、コスト削減や従業員の業務負担軽減にもつながるでしょう。
シフト管理システム
シフト管理システムとは、従業員のシフトをクラウド上で一元管理できるシステムをさします。製品によって利用可能な機能は異なりますが、一般的な機能は以下のとおりです。
- 勤怠管理機能
- 労務アラート機能(長時間労働や有給未取得の防止など)
- 休暇管理・申請機能
- シフト管理・自動作成機能
- スタッフ同士のコミュニケーション機能
- 作業割当機能
シフトの作成や共有、訂正がデータ上で可能になるため、効率的な人員配置、無駄の削減、急な欠勤への迅速対応などが可能になります。シフト管理者の業務軽減にもつながり、従業員の満足度向上に貢献するでしょう。
ダイナミックプライシング
「ダイナミックプライシング」とは、商品やサービスの需要に応じて価格を変動させることです。この仕組みを導入することは、働く価値が多様化している時代に適合しています。
具体的には、スタッフのシフトや人件費を必要に応じて最適化します。
例えば、ピークタイムや繁忙期、特別なイベント時は人員調整(週末や特定の時間帯含め)が必要です。そこで、業務の忙しさに応じてダイナミックプライシングで時間給を上げてスタッフを確保すれば、従業員のモチベーションを高めることができ、同時に顧客対応の質も向上が期待できます。
ダイナミックプライシングは、シフト管理にも適用可能なので、人手不足解消のひとつの手段になるでしょう。
スーパーの人手不足を解消するツール・システムの導入事例
九州に本拠地を置き、人手不足解消に貢献する様々なシステムやツールを導入している大型スーパーの事例を紹介します。企業が展開する一部の店舗では、スマートショッピングカートやセルフレジを導入しており、レジ時間の約75%を削減、レジの人件費も約2割の削減に成功しています。
顧客はお買い物をしながらレジカートのタブレット端末でバーコードを読み取るため、会計時にレジ打ちを待つ必要がありません。また、専用のプリペイドカードが使えるため、残高をチャージしておけば現金を用意する必要もなく、スムーズにお買い物が完了します。
レジスタッフの業務を削減でき、人手不足の解消に貢献している上、顧客の満足度向上にもつながっている事例です。
スーパーや飲食店の人手不足解消を目指すなら「スマートレストランEXPO」へ
スーパーや飲食店の経営で人手不足に悩んでいるなら、ぜひ「スマートレストランEXPO」にご来場ください。「スマートレストランEXPO」とは、飲食店の自動化・DXに特化した展示会です。
人手不足問題・労働環境の改善などの課題を先端テクノロジー(ロボット・IoT・AIなど)で解決する企業が、最新技術や製品を出展します。
事前登録すれば無料で入場可能で、配膳ロボットやセルフレジ、キャッシュレス決済システムなど、スーパーや飲食店の業務効率化に有効な製品も多く出展するため、人手不足解消に向けた情報収集の場としてご活用いただけます。
なお、来場だけでなく出展者側として参加することにもメリットがあります。スーパーや飲食店をはじめとする業種の経営、システム、店舗開発部門の方々などが集まるなかで自社の製品を大いにアピールできる他、導入を前向きに考えている企業と商談でき、案件の獲得につながります。
来場、出展ともにメリットがあるので、ぜひ参加をご検討ください。
スーパーや飲食店の人手不足解消には業務の効率化が必須
小売店や飲食サービス業は人手不足が深刻化している業種のひとつです。人手不足解消のためには、労働条件の改善や採用強化などが挙げられます。人手を増やす方法以外では、業務効率化・自動化も人手不足解消に有効です。
キャッシュレス決済の対応やセルフレジの導入、シフト管理システムの導入は、人手不足解消に貢献するでしょう。しかし、導入コストや自社に適した製品がわからず、導入に踏み切れない方もいるかもしれません。
人手不足に悩んでおり、解決の手段を探しているのであれば、飲食店の自動化・DXに特化した展示会である「スマートレストランEXPO」にぜひ足をお運びください。人手不足や労働環境の課題を先端テクノロジーで解決する企業が、最新技術や製品を出展するため、有益な情報収集が可能です。
▶監修:宮崎 政喜(みやざき まさき)
エムズファクトリー合同会社 代表 / 料理人兼フードコンサルタント
出身は岐阜県、10代続く農家のせがれとして生まれ、現在東京在住。プロの料理人であり食品加工のスペシャリスト。また中小企業への経営指導、食の専門家講師も務めるフードコンサルタントでもある。飲食店舗・加工施設の開業支援は200店舗以上。料理人としてはイタリアトスカーナ州2星店『ristorante DA CAINO』出身。昨今、市町村や各機関からの依頼にて道の駅やアンテナショップも数多く手掛ける。今まで開発してきた食品は1000品目を越え、商品企画、レシピ開発、製造指導、販路開拓まで支援を日々実施している。
▼この記事をSNSでシェアする