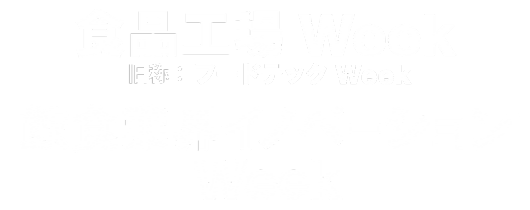顧客満足度(CS)を上げる方法とは?飲食店での具体例や経営における重要性を紹介
顧客満足度は経営にとって重要な意味を持ちます。しかし、顧客が何をもって満足するのか、具体的に何をすれば良いのかは業界や業種によって異なる他、顧客の年齢層や目的によっても様々です。
本記事では、顧客満足度の概要や上げるメリットを紹介します。飲食店を例に、顧客満足度を上げるための具体例を紹介するので、顧客満足度を高めたいと考えている飲食店の経営者の方は参考にしてください。
「顧客満足度を上げる」とは?
顧客満足度とは、顧客が商品やサービスを利用した際に感じる「満足の度合い」を数値や指標で表したもので、CS(Customer Satisfaction)とも呼ばれます。
企業が提供する商品やサービスが、顧客の期待やニーズをどれだけ満たしているかを示す重要な指標であり、マーケティングや経営戦略にとって欠かせない要素です。
「顧客満足度を上げる」とは、顧客が商品購入やサービス利用に関して、事前に期待している結果よりも満足する結果を与えることを意味します。顧客満足度は、単に「良い・悪い」などの評価にとどまらず、リピートの意思決定や他人への口コミ効果などにも影響を与えます。
顧客満足度(CS)を上げることが重要視されている背景
企業にとって、顧客が再購入してくれるかどうかは経営を維持する上で重要な要素です。顧客満足度を上げることはリピートの判断に大きく影響するため、重要視されています。新規顧客獲得よりも「既存顧客をいかに維持し、長期的な関係性を築くか」が企業成長の鍵となっており、顧客満足度の向上が顧客のロイヤルティを高め、LTV(顧客生涯価値)の最大化に直結しています。
顧客のロイヤルティとは、顧客が特定の企業やブランド、商品、サービスに愛着や信頼を持つことです。LTVとは、顧客が自社の商品・サービスを利用開始してから終了するまでの間に、どれだけ利益を得ることができたのかを表す指標です。
加えて、近年では以下の背景も顧客満足度を上げる必要性が高まっている要因として挙げられます。
- 顧客ニーズの多様化
- SNSやレビューサイトの口コミにおける影響力の拡大
- 競争激化による差別化の必要性の高まり
インターネットやスマートフォンの普及により、消費者が情報を簡単に入手できるようになました。その結果、商品やサービスを比較検討する選択肢が増え、ニーズが多様化しています。
飲食業界を例に挙げると、健康志向、簡便化志向、経済性志向など、重視するものは年齢や価値観、年収によって異なり、サービスを提供する側が顧客満足度を高めるためには、顧客ニーズを正確に捉えなければなりません。
また、現代は顧客の感想や評価がSNSやレビューサイトの口コミ、動画投稿などを通じて瞬時に拡散されます。ポジティブな評価は広告効果につながりますが、ネガティブな評判は大きな損害につながるため、日頃から顧客満足度を高く維持することが大切です。
さらに、消費者はインターネットを通じて簡単に他社製品と比較できるため、簡単に乗り換えが可能です。とくに飲食店は競合が多いため、単に品質や価格だけで競争するのではなく、顧客に「この企業を選びたい」と感じてもらうための付加価値が求められます。
他社との差別化を図れる戦略のひとつが、顧客満足度の向上といえるでしょう。
顧客満足度(CS)を上げるメリット
顧客満足度を高めることにより得られるメリットは、主に以下のとおりです。
- 口コミによる新規顧客層の獲得や広告費の削減
- ファン層やリピーターの増加
- 企業価値の創出や向上
- 従業員のモチベーションの向上
- 売上の向上や価格競争の回避
それぞれ詳しく紹介します。
口コミによる新規顧客層の獲得や広告費の削減
顧客満足度が高まると、利用者が自らSNSや口コミで商品やサービスの魅力を発信してくれる機会が増えます。近年はSNSを通じて得られる情報や口コミなど、リアルな声を重視する消費者が増えているため、ポジティブな口コミ自体が宣伝効果をもたらす可能性があります。
口コミによる評判が拡散されれば、企業が多額の広告費を投じなくても新規顧客を自然に呼び込めるでしょう。結果的に、広告や販促にかかるコストを抑えつつ、効率的に認知度を拡大できます。
ファン層やリピーター、ロイヤルカスタマーの増加
顧客が商品やサービスに満足すると、企業やお店に対する信頼や愛着が高まり、リピートにつながります。顧客満足度は、ファン層やリピーター、そしてより強固な関係を築くロイヤルカスタマーを獲得する上で欠かせない要素です。
ロイヤルカスタマーは、SNSを通じて自発的に情報を広めてくれるなど、広告以上の影響力をもたらす存在です。価格だけで他社に乗り換えることが少なく、安定した売上の源となります。また、新商品の発売時にも積極的に関心を寄せ、特別な販促をしなくても購入してくれるケースが多く見られます。
満足を超えて「共感」や「信頼」を育むことが、長期的なビジネスの成長に直結します。
企業価値の創出や向上
顧客満足度が高い企業は、「顧客を大切にする企業」として評価され、社会的な信頼や好感度が高まります。
顧客を大切にし、信頼を得ている企業は、株主や投資家、取引先など多くのステークホルダーに対してもプラスの印象を与えるでしょう。
資金調達の難易度が低下したり、取引先の獲得・拡大につながったりするなどのメリットが期待されます。
従業員のモチベーションの向上
顧客からの高評価や感謝の声は、働く従業員のモチベーションに大きく影響します。顧客に喜ばれていると実感できることが、従業員にとってやりがいや誇りにつながるかもしれません。職場への愛着は、自然と仕事への責任感や主体的な行動にも波及します。
例えば飲食店の場合、従業員のモチベーションが高まることで接客の質が向上し、さらに顧客満足度が上がるという好循環が生まれます。
実際、某コーヒーショップでは「従業員を大切にする文化」を徹底することで、スタッフのホスピタリティがブランドの魅力となり、世界的なファンを獲得するまでに成長しました。従業員満足と顧客満足が連動することを示す代表的な成功事例といえるでしょう。
売上の向上や価格競争の回避
顧客満足度が高まると、顧客はその企業の商品やサービスに対して強い信頼を抱くようになります。ブランド力の向上により、他社より多少価格が高くても購入してもらえるかもしれません。
競合他社を意識した過度な値下げや高い頻度でのキャンペーンに頼る必要がなくなり、健全な価格設定による安定した売上の維持が可能になります。
顧客満足度(CS)を上げる際の指標
顧客満足度を上げる際に意識する指標として、以下の4つを紹介します。
必要に応じて指標を活用して、自社の商品・サービスに対する顧客満足度の現状を客観的に把握し、改善の方向性を明確にしましょう。
顧客満足度の調査方法
顧客満足度調査を調査する方法には、様々な手法があります。一例は以下のとおりです。
- インターネット調査
- アンケート調査
- 顧客へのヒアリング
- モニタリング調査
- ミステリーショッパー(覆面調査)
自社で行う他、顧客満足度調査を専門とする企業をはじめとする外部機関に依頼する方法などがあります。コストや手間を考慮しつつ、自社に適した方法で定期的に行いましょう。
顧客満足度(CS)を上げる方法|飲食店の場合の具体例
顧客満足度を上げる方法は業界・業種によって異なります。飲食店を例にして紹介すると、以下のとおりです。
- 顧客目線で商品・サービスを見直す
- 顧客の声を反映した商品・サービスの提供を行う
- 顧客とのコミュニケーション手段を取り入れる
- QSCを改善・向上する
- 顧客管理システム(CRM)をはじめとするシステム・ツールを導入する
それぞれ具体例を挙げつつ紹介するのでぜひ参考にしてください。
顧客目線で商品・サービスを見直す
飲食店で顧客満足度を高めるには、まず「お店側」ではなく「顧客」の目線に立って、商品やサービスを見直すことが重要です。顧客のニーズは、年齢や価値観、来店の目的などによって異なるため、自社の顧客層を見極めましょう。
例えば、ひとりで飲食店を選ぶ際には料金や提供までの待ち時間が重視されやすい傾向にあります。この場合、「提供スピードを短縮する」「カウンター席を増やす」「ワンコインランチなどコストパフォーマンスを重視したメニューを提供する」などが顧客満足度を向上させるでしょう。
一方、デートや特別な日の外食では味や見栄えが重視されるかもしれません。「写真映えする華やかな料理やデザートを用意する」「照明やBGMで雰囲気作りに配慮する」「サプライズのサービスに対応する」などが顧客満足度に直結する可能性があります。
単純な価格だけでなく、顧客ごとのニーズを満たすことで顧客満足度が高まります。
顧客の声を反映した商品・サービスの提供を行う
顧客満足度を上げるためには、アンケートなどを通じて顧客からのフィードバックを得ることが大切です。現場の見えない課題が浮き彫りになり、顧客満足度を上げるための具体策の策定につながります。
例えば「料理は美味しいが提供が遅い」「BGMの音量が気になる」などの些細な意見でも、参考にして改善すれば、顧客満足度が向上する可能性があるでしょう。
調査は一度で終わりにせず、定期的に行い、改善し続けることが重要です。
顧客とのコミュニケーション手段を取り入れる
飲食店で顧客満足度を高めるには、一方通行の発信だけでなく、顧客と双方向でつながるコミュニケーションが有効です。SNSや公式サイトの投稿、お店のブログのコメントなどを活用して、顧客からの問合せや感想に迅速かつ丁寧に対応しましょう。
例えば「過去のメニューを復活してほしい」とSNSで投稿されていた場合には、責任者に顧客の要望を伝え、顧客へ回答することもひとつの方法です。何気ない感想や写真の投稿に関しても、コメントを返信するだけでも効果があるかもしれません。
要望への対応報告などを通じて「意見がきちんと届いている」と感じてもらうなど、コミュニケーションを積み重ねることで顧客にとって「特別なお店」になり、愛着や信頼が生まれ、リピーターやファンになる可能性が高まります。
とくに小規模飲食店の場合は、「食+人+空間」が一体となった体験業態で、小規模だからこそできる「気づき・覚えている・話しかける」の積み重ねが、顧客満足度を向上させる大きな施策につながります。
例えば、カウンター客や3回目来店の方に「常連さん向け裏メニュー」を提供することで、特別感や常連になる喜びを感じ、顧客満足度を超えたファン化に直結します。
また、個別に声かけをすることで再来にもつながります。人(スタッフ)に顧客がつく体験を増やしていくことが、DXが進む昨今で最も重要です。
QSCを改善・向上する
QSCは「Quality(品質)」「Service(接客)」「Cleanliness(清潔さ)」の頭文字を取った言葉です。飲食業やサービス業で顧客満足度を高めるための指標として活用されます。
大手企業でも、顧客満足度を高めるためにQSCを徹底している企業も少なくありません。QSCの改善・向上には顧客満足度を高めること以外にも様々なメリットがあります。具体的なメリットは以下のとおりです。
- 顧客ニーズの多様化への対応
- 売上向上と収益の安定化
- ブランドイメージ向上と他社との差別化
- クレーム・トラブルの軽減
- 従業員のモチベーション維持・向上
顧客満足度調査とあわせてQSCを実践することで、競合との差別化を図りつつ、顧客満足度の向上が期待できます。
QSCについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
顧客管理システム(CRM)をはじめとするシステム・ツールを導入する
顧客満足度を高めるために、顧客関係管理(CRM:Customer Relationship Management)を行う顧客管理システムを導入するのも選択肢のひとつです。
顧客関係管理システムとは、顧客との関係を深め、長期的な信頼関係を築くことで、企業の売上や収益の向上を図る経営手法やシステムをさします。
CRMの活用し、顧客の基本情報や来店履歴、過去の注文内容、アンケート結果などをもとに、顧客に合わせたサービス提供が可能になります。
常連客に好みのメニューを提案したり、来店頻度に応じた特典を用意したりするなど、きめ細やかな対応が実現できるシステムです。データを活用して分析すれば、満足度の高い時間帯や人気メニューなどを把握し、営業戦略にも活かせます。
CRM以外にも、業務効率化や自動化を実現するシステム・ツールは様々な種類があります。
- モバイルオーダーシステム
- 配膳ロボット
- スマートキッチン
- 調理ロボット
- シフト管理ツール
- 在庫管理システム
- 予約管理システム
システム・ツールの導入自体が顧客満足度の向上につながるケースがあります。
例えば、モバイルオーダーシステムを導入すれば、注文対応にかかる従業員の業務負担を軽減することが可能です。顧客は混雑時でも店員がテーブルに注文を取りに来るまで待つ必要がなく、スムーズに商品を注文できます。
また、配膳ロボットや調理ロボットは、従業員の作業負担を軽減します。業務負担が軽減されれば、顧客との密なコミュニケーションや細やかなテーブルチェックなど、顧客満足度を上げるための業務に集中できるため、従業員・顧客双方にとって有益といえるでしょう。
飲食店の業務効率化についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
顧客満足度を上げるための取り組み事例|飲食店・小売店の場合
飲食店・小売店で顧客満足度を上げることに成功している事例として、以下の3社を紹介します。
- マクドナルドの事例
- ファミリーマートの事例
- すかいらーくホールディングスの事例
それぞれ参考にしてください。
マクドナルドの事例
マクドナルドは「QSC(品質・サービス・清潔さ・価値)」を経営の基盤とし、1955年の創業時からマニュアル化して徹底している企業です。現在でも、QSCにV(Value)を加えた「QSC&V」を徹底し、サービスを提供しています。
品質では世界共通の味を守るため厳格な基準を設け、サービス面では心のこもった対応と快適な空間づくりを重視しています。創業者がこだわったとされる清潔さも徹底されており、厨房設計にも反映されています。
Q・S・Cを高いレベルで維持することで「価値(Value)」が生まれ、顧客満足へとつながるとの理念で運営されている企業です。
ファミリーマートの事例
ファミリーマートは、顧客に選ばれるために「商品の品質」と「お店の品質」を高めることを重視している企業です。「QSCレベルの向上」を最重要目標に設定し、教育制度にもQSCを活用しています。
従業員を評価し、本部社員として登用する「エクセレントトレーナー」制度や、独自の人材育成システム「ストアスタッフトータルシステム(SST)」、優れた店舗を表彰する「QSCアワード」などを通じて、全国的なQSC向上を推進している企業です。
すかいらーくホールディングスの事例
飲食店を経営するすかいらーくホールディングスは、2022年にQSC向上委員会を発足し、お客さまからの声に対して迅速に対応できる体制を整えている企業です。
お客様相談室に寄せられたご意見・ご要望を、全経営層・全部門が毎日閲覧できる仕組みを構築することで、業務運営の見直しや商品・サービスの改善を実施しました。
また、社員・アルバイト従業員を対象に勉強会も定期的に開催しています。良いサービスについて、意見を出し合い自発的に考えた行動を促すことを目的としています。実際にクレーム件数の減少とお褒めの件数が増加しました。
その他、様々な食のニーズに対応するため、POSによる販売実績データやアプリなどのビッグデータを活用・分析し、メニュー開発やサービスの改善に取り組んでいます。
これらの取り組みにより、お客様総合満足度は、2021年の73%から2024年には87%へと上昇しました。
顧客満足度の向上を目指しているなら「飲食業界イノベーションWeek」で情報収集を
飲食店の経営に携わっており、顧客満足度の向上を目指しているなら、ぜひ「飲食業界イノベーションWeek」へご来場ください。飲食業界イノベーションWeekは、飲食店が抱える様々な悩みや課題を解決する最新テクノロジーやサービスが出展する展示会です。
飲食チェーン、個人経営の飲食店、小売店、ホテルなどが課題解決のヒントを求め、全国各地から来場します。
人手不足解消や集客支援など飲食店のお悩み解決に繋がる最新サービスが出展する「スマートレストラン EXPO」や、飲食店の経営や店舗管理の課題を解決するための専門展「レストランマネジメントEXPO」の2つで構成されています。
「スマートレストランEXPO」は、人手不足、自動化・業務効率化などの課題を解決するための調理ロボット、AI、POSなどが出展する展示会です。「レストランマネジメントEXPO」では、受発注システム、勤怠管理システムなど、店舗管理の課題を解決するためのサービスが出展します。
人手不足や業務負担など、様々な理由で顧客満足度を上げるための施策にリソースが割けない方は、ぜひ展示会にご来場ください。
展示会は事前登録すれば無料で入場可能です。顧客満足度を上げるために役立つ情報の収集や製品・サービスの比較の機会にご活用ください。
また、展示会は出展側としての参加も可能です。飲食店をはじめとする業種の経営、システム、店舗開発部門の方々が来場するため、自社製品の認知度向上や他社との商談の機会にもつながります。
顧客満足度を上げることは継続的な経営に欠かせない要素
顧客満足度は顧客の「満足の度合い」を数値や指標で表したものです。CSとも呼ばれ、自社が顧客のニーズをどの程度満たしているかを判断する指標になります。
近年はライフスタイルや価値観の変化により、顧客のニーズが多様化しています。とくに競合他社が多い飲食店などの業界では、価格競争に巻き込まれないためにも顧客満足度を上げ、自店舗のブランド力を高めることが継続的な経営の鍵となるでしょう。
飲食店の経営に携わっており、顧客満足度を上げる方法に悩んでいる方や、顧客満足度を高めることにリソースが割けず困っている方は、ぜひ「飲食業界イノベーションWeek」にご来場ください。
飲食業界イノベーションWeekを構成する「スマートレストランEXPO」「レストランマネジメントEXPO」を通じて、顧客満足度向上に貢献する有益な情報が得られます。来場側・出展側双方にメリットがあるため、ぜひこの機会にご検討ください。
▶監修:宮崎 政喜(みやざき まさき)
出身は岐阜県、10代続く農家のせがれとして生まれ、現在東京在住。プロの料理人であり食品加工のスペシャリスト。また中小企業への経営指導、食の専門家講師も務めるフードコンサルタントでもある。飲食店舗・加工施設の開業支援は200店舗以上。料理人としてはイタリア トスカーナ州2星店『ristorante DA CAINO』出身。 昨今、市町村や各機関からの依頼にて道の駅やアンテナショップも数多く手掛ける。今まで開発してきた食品は1000品目を越え、商品企画、レシピ開発、製造指導、販路開拓まで支援を日々実施している。
▼この記事をSNSでシェアする