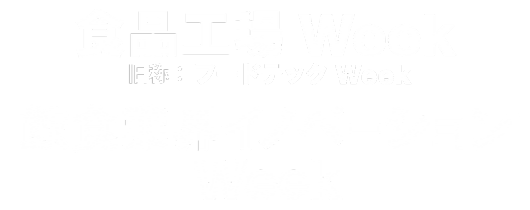ISO22000とは?食品安全に関する国際規格の概要や導入メリットをわかりやすく解説
近年、食品の安全性に関して規制が厳しくなっています。食品を扱う企業は法律に則った品質管理・衛生管理を行う他、取引先や消費者など外部に対しても安全性を証明できる取り組みを行うことが大切です。
ISO22000とは、食品安全に関する国際規格のひとつです。ISO22000の認証取得は、食品安全に関する国際的な取り組みを行っていることの証明になり、食品を取り扱う企業の経営に大きな影響を与えます。
本記事では、ISO22000の概要や特徴、目的、導入メリットや注意点を紹介します。ISO22000とFSSC22000の違い、令和3年に義務化されたHACCPとの違いも紹介するので、ISO22000の取得を目指している企業の方や、具体的な内容・効果を知りたい方はぜひ参考にしてください。
ISO22000とは
ISO22000は、食品安全を確保するための国際的なマネジメントシステム規格です。国際標準化機構(ISO)が2005年に初版を発行し、2018年に最新版(ISO22000:2018)が発行されました。ISO22000はHACCP(ハサップ)の考え方を取り入れつつ、ISOのマネジメント手法(PDCAなど)を組み合わせている点が特徴です。
食品の製造、加工、流通、サービスなど、あらゆる食品関連事業者が対象になっています。具体的には以下のとおりです。
- 作物生産業者、飼料製造業者
- 食品製造業者
- 輸送および保管業者、下請負契約者
- 小売業者
- 清掃・洗浄、殺菌・消毒等のサービス業者
- 食品包装・包装資材製造業者
- 添加物・香料等の化学品製造業者
- 農薬、肥料、洗浄剤等の製造業者
また、ISO22000では、消費者に安全な食品を提供するための体制構築を目的として、「食品安全マネジメントシステム(FSMS)」の確立と運用に関する具体的な要求事項が定められています。
要求事項とは、基本的な取り組みを示したもので、例えば以下のような内容が含まれます。
- 組織の状況
- リーダーシップ
- 計画
- 支援
- 運用
- パフォーマンス評価
- 改善
FSSC22000との違い
ISO22000とFSSC22000は、どちらも食品安全マネジメントシステムの国際規格ですが、目的や構成に明確な違いがあります。
ISO22000は、食品安全管理の基本的な仕組みを提供する国際規格で、食品製造業に限らず、あらゆる食品関連事業に適用可能です。
一方、FSSC22000はISO22000を基盤としながら、安全なサービスの提供やアレルゲンの管理、ラベルに関する事項など、実務的で具体的な要求事項が追加されています。ISO22000では曖昧な表現だった部分を具体化するなど、実運用レベルでの管理が強化されている点が特徴です。
FSSC22000は、ISO22000より実践的かつ国際的な信頼性を備えた認証と位置付けられる規格です。FSSC22000へのステップアップを目指すなら、まずはISO22000の要求事項を満たすことを目指しましょう。
HACCP(ハサップ)との違い
HACCP(ハサップ)とISO22000やFSSC22000は、全て食品安全に関する仕組みですが、それぞれの役割や位置付けに違いがあります。
HACCPは、食品の製造工程の危害要因(微生物、化学物質、異物など)を分析した上で、特に重要な工程を設定し、継続的に監視・記録する衛生管理手法です。
令和3年6月1日から、原則として全ての食品等事業者に対してHACCPに沿った衛生管理が義務付けられました。
一方、前述のとおりISO22000はHACCPの考え方を含んだ上で、組織全体で食品安全を管理・改善していくためのマネジメントシステム規格です。FSSC22000は、ISO22000をベースにしつつ、より具体的で実務的な管理基準や追加要求事項を組み合わせたものです。
つまり、HACCPは「方法論(手法)」、ISO22000は「仕組み」、FSSC22000はISO22000からさらに具体化された国際規格という位置付けになります。
ISO22000やFSSC22000はHACCPを認証基準に含んでいるため、認証を取得していると、HACCPに関連する審査が簡略化できるなどのメリットがあります。
HACCPについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
ISO22000の特徴・目的
ISO22000の大きな特徴は、食品安全のリスク管理手法であるHACCPの考え方をベースに、企業全体のマネジメントシステムと統合している点です。ISO22000を参考にすることで、衛生管理だけでなく、組織全体で食品安全に取り組む体制を構築できます。
一般社団法人日本能率協会審査登録センターで紹介されているISO22000取得の目的は、以下のとおりです。
ISO22000は、ISO9001(品質)やISO14001(環境)と同様の構成にマネジメントシステムの原則が盛り込まれている規格のため、ISO9001やISO14001と統合運用がしやすい点もメリットです。
PDCAサイクルを通じた継続的改善の仕組みが備わっており、食品安全だけでなく組織の信頼性や生産性の向上にも貢献します。
ISO22000が注目されている背景
ISO22000やFSSC22000が注目されている背景には、以下の要因が挙げられます。
- 食品の安全性に対する意識の高まり
- HACCPの義務化
- 国際取引の増加
食品にまつわる事故は毎年発生しており、直近5年では食中毒だけでも年間700〜1,100件発生しています※1。令和6年の食中毒の事件数は1,037件で、患者数は1万4,229人、うち死者3人です※2。
食品事故の増加から、食品の安全性に対する意識が高まり、令和3年6月にはHACCPに沿った衛生管理が義務化されました。
認証基準にHACCPの考え方が含まれたISO22000の取得は、安全性を示すことにつながります。前述のとおり、ISO22000やFSSC22000の取得により、HACCPの審査が簡易化されることも期待できます。
また、食品業界では大手企業を中心にグローバル化が加速しており、国内市場の縮小を見越して、海外展開を視野に入れる企業も増えているのが現状です。そのため、国際的に通用する規格であるISO22000やFSSC22000を取得することで、海外企業との信頼構築や取引条件の整備につながる点も、注目される一因です。
※1 出典:農林水産省「食中毒は年間を通して発生しています」
※2 出典:厚生労働省「令和6年食中毒発生状況の概要」
ISO22000の規格取得は義務?
ISO22000やFSSC22000などの食品安全マネジメントシステムの規格取得は、法律による義務ではありません。認証を取得しなくても食品製造や販売は可能です。
一方、HACCPに基づく衛生管理は、日本では令和3年6月1日から原則全ての食品事業者に対して義務化されています。そのため、HACCPに沿った衛生管理は行わなければなりません。
ISO22000やFSSC22000にはHACCPの考え方が含まれているため、認証を取得することは、HACCPに沿った衛生管理にもつながります。加えて、組織全体で食品安全に取り組む体制や、安全性の対外的なアピールにもつながるなど、メリットが多くあります。
例えば、取引先にISO22000の取得を打診する企業もあるため、取得により取引先の拡大が期待できるかもしれません。法的な義務ではないものの、取引や事業展開を検討する上での必須条件となる場合もあります。
ISO22000の規格取得方法や取得までの流れ
ISO22000の規格を取得するためには、認証機関(審査登録機関)と呼ばれる第三者機関に申し込みます。一般財団法人日本品質保証機構や一般社団法人日本能率協会審査登録センターが一例です。
審査を受ける前に、自社の食品安全に関する取り組みや管理体制が、ISO22000の要求事項とどの程度合致しているかの確認が大切です。現状を把握した上で、取得に向けた社内体制を構築しましょう。
準備が整ったら登録の審査を行います。取得までの大まかな流れは以下のとおりです。
ISO22000取得によるメリット
ISO22000取得によるメリットは以下のとおりです。
- 食品の安全性確保とリスク低減
- 企業の信頼性・ブランド価値の向上
- 国内外での取引先拡大
- クレーム・リコールへの対応力強化
- 従業員の意識向上
- 食品ロス削減やサステナビリティへの貢献
それぞれ詳しく紹介します。
食品の安全性確保とリスク低減
ISO22000は、原材料の受け入れから出荷までのリスクを体系的に管理するためのマネジメントシステムであり、微生物汚染や異物混入、アレルゲンなどの食品事故の防止に貢献します。
衛生管理だけでなく、企業全体で食品の安全性を守る体制の構築を目的としている点もメリットです。運用後の評価・改善も含まれており、品質の安定と事故防止に関する継続的な改善が期待できます。
企業の信頼性・ブランド価値の向上
ISO22000の取得は、食品安全に関する国内外の法令や規制を適切に順守している体制を築いている証明になります。
表示偽装や異物混入の隠蔽などのコンプライアンス違反は、企業の信用失墜やブランドイメージの悪化につながるため、法令遵守の仕組みをマネジメントシステムとして整備することが重要です。
ISO22000はコンプライアンスを定着させるための枠組みを提供しており、基盤の強化につながるでしょう。ISO22000の認証を取得することで、顧客や取引先、消費者からの信頼を獲得しやすくなり、企業のブランド価値向上にもつながります。
国内外での取引先拡大
ISO22000は国際的に認められた食品安全マネジメント規格です。認証を取得することで、国内だけでなく海外の取引先に対しても食品安全への取り組みを客観的に示すことが可能です。
近年は、海外輸出やグローバル企業との取引を進める上で、国際基準への対応が求められることが増えており、ISO22000取得がその条件となるケースもあります。
認証取得により、国内市場だけでなく、海外市場も視野に入れた販路開拓やビジネスチャンスの拡大も期待できます。
クレーム・リコールへの対応力強化
ISO22000では、品質管理だけではなく、リスクの事前予測や管理、万が一トラブルが発生した際の対応体制の構築も含まれています。
そのため、ISO22000を取得し運用することで、クレームや食品事故の防止につながります。万が一リコールが発生した場合でも、迅速かつ的確に対応できる体制を整えることが可能です。
危機管理能力の高さは、競合との差別化にもつながります。
従業員の意識向上
ISO22000の運用は、現場を含む全従業員で行うものです。認証取得により、食品安全に関する教育や訓練が実施されれば、組織全体に適切な知識と意識が浸透していきます。
従業員一人ひとりが自らの業務と食品安全との関係を理解することで、日常の行動が変わり、ヒューマンエラーの減少や衛生管理の徹底が期待できます。
ISO22000は単なる規格ではなく、組織の文化づくりにも貢献する仕組みです。
食品ロス削減やサステナビリティへの貢献
ISO22000では、食品の安全性を確保する過程で、不適合品の発生防止や在庫ロスの削減にもつながる仕組みが整備されます。
その結果、食品廃棄の低減や生産工程の最適化が図られ、食品ロス削減や持続可能な生産体制の構築に寄与します。
近年、サステナビリティやSDGsへの取り組みが評価されているなか、ISO22000の導入は社会的信頼性の強化にも直結するでしょう。
ISO22000取得のデメリット・注意点
ISO22000の認証を取得することに、大きなデメリットはありません。食品を取り扱う企業であれば、取得によるメリットの方が多くあります。あえて注意点を挙げると以下のとおりです。
- 認証取得にあたりコストがかかる
- 要求事項に対応するため手間がかかる
それぞれ詳しく紹介します。
認証取得にあたりコストがかかる
ISO22000の取得には、一定のコストがかかることを理解しておく必要があります。主な費用は以下のとおりです。
- 文書整備やマニュアル作成にかかる人件費
- 従業員への教育・訓練費
- 審査機関による初回審査や登録費
認証後も毎年の定期審査や更新審査が必要なため、維持費も発生します。また、費用は規模や内容によって異なります。
ISO22000の審査を行っている一般社団法人日本能率協会審査登録センターの情報を参考にすると、20〜30人規模の食品工場の場合、以下が費用相場として紹介されています。
規模や業態によっても異なるため、取得を検討している場合は事前に見積もりを取りましょう。
中小企業にとっては、費用負担が大きなハードルとなることがあるかもしれません。費用対効果を慎重に見極めた上で、取得するかどうか検討することが大切です。
要求事項に対応するため手間がかかる
ISO22000の取得には、規格に定められた様々な要求事項に対応する必要があります。既存の業務フローの見直しや衛生管理の再構築、文書化された手順や記録の整備、リスクアセスメントの実施などが一例です。
取得の体制を構築するまでには時間と労力がかかるため、理解した上で検討しましょう。
また、ISO22000の取得後にも、マネジメントシステムの有効性を確認するためのサーベイランス審査が毎年行われる点にも注意が必要です。
ISO22000取得による効果の事例
ISO22000取得による効果の事例をいくつか紹介します。
顧客の要請や内部統制強化のために、ISO22000を取得したお菓子の開発・製造を行う企業では、取得から2年でクレーム発生率が3分の1に減少する成果を上げています。
また、お菓子を製造・販売する別の企業では、食品安全マネジメントシステムの構築やブランドイメージ向上のためにISO22000を取得した結果、食品安全に関する組織体制が整い、時間短縮とコスト削減に成功しています。
さらに、ISO9001を取得した4年後にISO22000を取得している食品メーカーの事例もあります。この企業では、ISO9001で基盤を築き、より実効性のあるISO22000によりリスクの管理体制を構築したことで、組織全体の意識改革や内部監査の質の向上に成功しています。
ISO22000取得に向けて食品安全の対策強化に興味があるなら「食品衛生イノベーション展」へ
ISO22000取得に向けて食品安全の対策強化に興味があるなら、ぜひ「食品衛生イノベーション展」にご来場ください。食品衛生イノベーション展は、食品衛生・食の安全の課題を解決する技術・サービスが出展する展示会です。
展示会には、異物混入対策、品質鮮度保持、洗浄・殺菌、クリーン・衛生、HACCP管理などを求め、全国の食品メーカーが来場します。有力企業の取り組み事例や規制対応に関するセミナーも開催されるため、食品安全に関する最新情報を得ることが可能です。
ISO22000取得に直結する、食品安全の対策強化に貢献する技術・サービスに興味がある方はぜひご来場ください。
展示会は事前登録すれば無料で入場可能です。関連サービスや製品を扱う企業なら出展側での参加も可能なため、自社製品の認知度向上の場や、新規リード獲得・営業強化の機会にもご活用いただけます。
■食品衛生イノベーション展
東京展:2025年12月3日(水)~5日(金) @幕張メッセ
大阪展:2026年9月30日(水)~10月2日(金) @インテックス大阪
ISO22000取得は食品の安全性と企業価値を向上させる
ISO22000は食品安全を確保するための国際的なマネジメントシステム規格です。HACCPの考え方をベースにしているため、取得によりHACCPに関する審査が簡略化されることも期待できます。
ISO22000の認証取得後は、より具体化されたFSSC22000へのステップアップも見込めます。食品の安全に対して取り組んでいる姿勢を示せることで、取引先や消費者からの信頼を獲得できるなど、様々なメリットがあります。
近年では食の安全に関する規制が強化されているため、企業によっては取引先の選定にISO22000やFSSC22000の認証が必須条件になっていることもあります。
ISO22000の取得に向けて食品の安全対策強化を検討しているなら、ぜひ「食品衛生イノベーション展」にご来場ください。会場ではISO22000取得に直結する、食品安全に関連する情報や食品衛生のトレンドに関する情報の収集が可能です。来場側、出展側の双方にメリットがあるため、ぜひこの機会にご検討ください。
■食品衛生イノベーション展
東京展:2025年12月3日(水)~5日(金) @幕張メッセ
大阪展:2026年9月30日(水)~10月2日(金) @インテックス大阪
▶監修:宮崎 政喜(みやざき まさき)
エムズファクトリー合同会社 代表 / 料理人兼フードコンサルタント
出身は岐阜県、10代続く農家のせがれとして生まれ、現在東京在住。プロの料理人であり食品加工のスペシャリスト。また中小企業への経営指導、食の専門家講師も務めるフードコンサルタントでもある。飲食店舗・加工施設の開業支援は200店舗以上。料理人としてはイタリア トスカーナ州2星店『ristorante DA CAINO』出身。 昨今、市町村や各機関からの依頼にて道の駅やアンテナショップも数多く手掛ける。今まで開発してきた食品は1000品目を越え、商品企画、レシピ開発、製造指導、販路開拓まで支援を日々実施している。
▼この記事をSNSでシェアする